ステークホルダーダイアログ Stakeholder Dialogue
ステークホルダーとのコミュニケーション
株主・投資家、お客様、取引先、従業員、地域社会、地球環境
「小牧市自然共生パートナーシップダイアログ2024」の開催
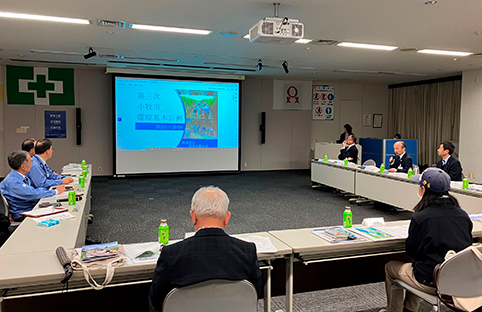
住友理工グループでは、CSR・サステナビリティ経営を進める上であらゆるステークホルダーとの双方向のコミュニケーションが重要であると考えています。
当社グループでは、天然ゴムをはじめ、大気や水、鉱物などの様々な自然の恵みを利用して事業活動を行っています。一昨年策定した「住友理工 環境長期ビジョン2050」では、これら自然の恵みや自然環境を事業活動によって破壊することなく、後世に引き継いでいく責任があることを認識し、自然共生へ貢献することを掲げています。本ビジョンの実現に向けて、小牧本社・製作所が所在する愛知県小牧市にて自然共生に関わる小牧市の多様なセクター(企業・行政・市民団体・大学など)による協働をより強固にし促進することで、小牧市の自然共生活動がより活気づくことを期待し、今年度で第2回目となる「小牧市自然共生パートナーシップダイアログ2024」を開催しました。
当社グループでは、天然ゴムをはじめ、大気や水、鉱物などの様々な自然の恵みを利用して事業活動を行っています。一昨年策定した「住友理工 環境長期ビジョン2050」では、これら自然の恵みや自然環境を事業活動によって破壊することなく、後世に引き継いでいく責任があることを認識し、自然共生へ貢献することを掲げています。本ビジョンの実現に向けて、小牧本社・製作所が所在する愛知県小牧市にて自然共生に関わる小牧市の多様なセクター(企業・行政・市民団体・大学など)による協働をより強固にし促進することで、小牧市の自然共生活動がより活気づくことを期待し、今年度で第2回目となる「小牧市自然共生パートナーシップダイアログ2024」を開催しました。
関連情報
【テーマ】「続・点の活動から面の活動へ」
~多様なセクターによる自然共生社会の実現~
小牧市内には小牧山、兒(ちご)の森などの豊富な自然がありますが、特定外来生物に指定されている動植物が市内で確認されており、在来種への影響が懸念されています。自然共生における生物多様性を保全するためには、自然環境を保護することの重要性が求められており、小牧市では自然を保全・再生し、生態系を回復する取り組みを推進しています。
第2回目となる今回のテーマは「続・点の活動から面の活動へ ~多様なセクターによる自然共生社会の実現~」とし、当日は小牧市副市長をはじめ、愛知県、小牧市役所、市民団体、大学の有識者に加え次世代を担う学生の皆さまにお集まりいただきました。まずは、前回ダイアログ起点でのパートナーシップで成し得た各団体の活動紹介とその効果を共有した上で、小牧市を“未来に繋げる豊かな自然と人がともに生きるまち”にするために、私たちができることを考え、共通目標策定に向けた対話を行いました。
第2回目となる今回のテーマは「続・点の活動から面の活動へ ~多様なセクターによる自然共生社会の実現~」とし、当日は小牧市副市長をはじめ、愛知県、小牧市役所、市民団体、大学の有識者に加え次世代を担う学生の皆さまにお集まりいただきました。まずは、前回ダイアログ起点でのパートナーシップで成し得た各団体の活動紹介とその効果を共有した上で、小牧市を“未来に繋げる豊かな自然と人がともに生きるまち”にするために、私たちができることを考え、共通目標策定に向けた対話を行いました。
参加者

●ファシリテーター
秦野 利基 氏/特定非営利活動法人こまき市民活動ネットワーク 顧問
●ステークホルダー
平岡 健一 氏/小牧市副市長
大島 孝士 氏/愛知県自然環境課 生物多様性保全グループ 主査
深見 優介 氏/愛知県自然環境課 生物多様性保全グループ 技師
中川 真徳 氏/小牧市役所 環境対策課 環境保全係 係長
若原 章裕 氏/小牧市役所 環境対策課 環境保全係 技師
郡 麻里 氏/名古屋経済大学 経営学部 准教授
橋場 隼希 氏/名古屋経済大学 経営学部 学生
中島 悠太 氏/名古屋経済大学 経営学部 学生
岡崎 朱里 氏/名古屋経済大学 経営学部 学生
小沢 通男 氏/大山川をきれいにする会 会長
馬場 容子 氏/兒の森活動グループ 会計
橋本 保 氏/ちごりんの里山 代表
●住友理工
清水 和志/執行役員社長
和久 伸一/専務執行役員
能祖 裕司/生産機能本部 副本部長
姉川 健治/小牧製作所 所長
棚橋 英明/環境推進部 部長
脇坂 治/経営企画部 部長
秦野 利基 氏/特定非営利活動法人こまき市民活動ネットワーク 顧問
●ステークホルダー
平岡 健一 氏/小牧市副市長
大島 孝士 氏/愛知県自然環境課 生物多様性保全グループ 主査
深見 優介 氏/愛知県自然環境課 生物多様性保全グループ 技師
中川 真徳 氏/小牧市役所 環境対策課 環境保全係 係長
若原 章裕 氏/小牧市役所 環境対策課 環境保全係 技師
郡 麻里 氏/名古屋経済大学 経営学部 准教授
橋場 隼希 氏/名古屋経済大学 経営学部 学生
中島 悠太 氏/名古屋経済大学 経営学部 学生
岡崎 朱里 氏/名古屋経済大学 経営学部 学生
小沢 通男 氏/大山川をきれいにする会 会長
馬場 容子 氏/兒の森活動グループ 会計
橋本 保 氏/ちごりんの里山 代表
●住友理工
清水 和志/執行役員社長
和久 伸一/専務執行役員
能祖 裕司/生産機能本部 副本部長
姉川 健治/小牧製作所 所長
棚橋 英明/環境推進部 部長
脇坂 治/経営企画部 部長
参加者の意見
—自然共生に関する参加者の取り組み
—“豊かな自然と人が共に生きるまち”を目指し、未来の子どもたちのためにできること
- 愛知県では各種制度を整備し、「環境都市あいち」実現のため生物多様性も推進している。
- 小牧市生物多様性地域戦略は、行政だけではなく、皆と一緒に取り組みを進めたい。
- 自然共生活動は長期的・計画的な活動が重要。近隣他企業とも連携し活性化させたい。
- 大学の講義の中で、学内樹木・外来生物の確認や大山川の植生調査などを行っている。
- 前回のダイアログでできた多様なセクターとの繋がりで新しいアイデアが生まれている。
- 環境や生物多様性活動ではあるが、地域交流も目的の1つとして活動している。
- ボランティアマッチングなどを活用して多くの人に活動を体験していただいている。
- 環境保全活動を中心に、子どもたちの未来のために人と森をつくることを目的に活動している。
- 自然は簡単に破壊することができるが、簡単に作ることはできない。保全・保護が重要。
—“豊かな自然と人が共に生きるまち”を目指し、未来の子どもたちのためにできること
- 活動範囲を拡大し誰でも来られる綺麗な森を目指し、子どもたちと除伐や間伐体験を進めたい。
- 幅広い世代のメンバーで継続的に活動できるようにしたい。
- 若者が一人で活動に参加するのはハードルが高い。学校の部活や、クラブチーム等のグループだと参加しやすい。
- 環境活動に参加する際にSNS用にカメラを貸与し撮影会を行うなど、別の付加価値を提供すると若者に受け入れられるのではないか。
- 学校で自然と触れ合えるような体験ができると、大人になってから環境問題に興味が出やすくなるのではないか。
- 生態系保全のためには、管理計画を事前にしっかり立てることが必要である。
ファシリテーター総括
人というのは自然の中で育てられて今があります。植物や動物や昆虫のみならず、人間がいかに幸せに生活していくか。人が生まれて育って家庭を持ってさらにそれが継続されていく営みにとって、やはり自然というのは無くてはならないものです。破壊された環境の中では、やはり人間は幸せに生きることが出来ません。それをいろいろな人たちが力を合わせて作っていく。その一つのテーマとして、住友理工の掲げる小牧モデルがあるのではないでしょうか。今後こういったつながりを作りながら、小さな子どもたちにまた活動に参加してもらえる、そんな社会になるべきだと思います。
自然共生は、地域と自然との関係、人と自然との関係、家族や人生と自然との関係、そして生活の糧となっている企業と自然との関係、公共や地域と自然との関係など、私たちの暮らしそのものではないかと思います。様々な観点で意見を交換することこそが、まさに「共生社会」の原点であることを強く感じた時間となりました。
このダイアログがきっかけとなり、さらに多くの人たちとつながりながら、小牧の自然共生社会が実現していくことを期待します。
自然共生は、地域と自然との関係、人と自然との関係、家族や人生と自然との関係、そして生活の糧となっている企業と自然との関係、公共や地域と自然との関係など、私たちの暮らしそのものではないかと思います。様々な観点で意見を交換することこそが、まさに「共生社会」の原点であることを強く感じた時間となりました。
このダイアログがきっかけとなり、さらに多くの人たちとつながりながら、小牧の自然共生社会が実現していくことを期待します。
2025年2月
特定非営利活動法人こまき市民活動ネットワーク
顧問 秦野 利基
特定非営利活動法人こまき市民活動ネットワーク
顧問 秦野 利基
ダイアログを終えて
参加者の皆さまには多くの発言、ご提案をいただき非常に有意義な対話の場となりました。自然は人の安らぎになるべきであり、まず身近な環境を大事にしたいという思いは強くあります。今回皆さまと共有できたものを活かし、更に仲間づくりを進め、今後も自然との共生、生物多様性保全のため、多様なセクターとの協働での対話および活動を推進・継続していきたいと考えています。
住友理工株式会社
第10回SDGs学生小論文アワード by 住友理工

「SDGs学生小論文アワード by 住友理工」は、住友理工への商号変更を記念する新たな社会貢献活動として、“未来を担う若者たちを応援する事業”と位置づけ、2015年より取組みを始めたプログラムです(設立時名称「住友理工学生小論文アワード」)。
このアワードをきっかけとし、全国の学生のみなさんが社会の課題や持続可能な社会づくりについて学び、考えた結果を論じる場の提供と、受賞をきっかけにさらに見聞を広め若者の成長に貢献することを目指しています。
2024年度は、“「オープンイノベーション」で社会課題を解決するには”をテーマに論文を募集。審査は、審査委員長の高村ゆかり氏(東京大学未来ビジョン研究センター教授)をはじめとする有識者の皆さまに加え、若者の思考や提案を取り入れ経営に生かすことを目的として、住友理工グループ従業員も一次審査に加わり、大賞(※今年度は最優秀賞相当と評価した論文が2本となったため、同格の大賞として決定)、優秀賞など5本の受賞論文を決定しました。1月には、大賞、優秀賞を受賞した13名の学生と審査委員、当社役員が参加する懇談会を実施。懇談会では、各受賞学生の応募論文についてのプレゼンテーションと質疑応答のほか、「2024年に向けた未来会議」と題し、2024~2050年の社会を見据えて策定した住友理工が実現したい未来像を説明した後、2050年はどのような世界になっているか、その中で自分はどうなっていたいか、住友理工の未来像に共感できるかなどの意見交換を実施しました。
今回で記念すべき10回目となる本アワードですが、1回目からの応募総数は768本、そして合計76本の論文を表彰してきました。
その受賞者の中には、本アワードで論じたこと、探求したことをきっかけに、日本だけではなく、海外や様々な最先端の業界で活躍をされている方が何人もいます。そんな皆さまからは、「このアワードで受賞したことが今のキャリアに繋がっている」などの嬉しい声もお寄せいただいています。
また、当社も受賞学生との懇談会を通して、今の若者の文化や発想に触れることにより気づかされることも多く、学生という次世代を担うステークホルダーとの対話を通じて、企業が目指すべき姿や、学生たちが関心を持っている社会課題などを知る大変貴重な機会となりました。
このアワードをきっかけとし、全国の学生のみなさんが社会の課題や持続可能な社会づくりについて学び、考えた結果を論じる場の提供と、受賞をきっかけにさらに見聞を広め若者の成長に貢献することを目指しています。
2024年度は、“「オープンイノベーション」で社会課題を解決するには”をテーマに論文を募集。審査は、審査委員長の高村ゆかり氏(東京大学未来ビジョン研究センター教授)をはじめとする有識者の皆さまに加え、若者の思考や提案を取り入れ経営に生かすことを目的として、住友理工グループ従業員も一次審査に加わり、大賞(※今年度は最優秀賞相当と評価した論文が2本となったため、同格の大賞として決定)、優秀賞など5本の受賞論文を決定しました。1月には、大賞、優秀賞を受賞した13名の学生と審査委員、当社役員が参加する懇談会を実施。懇談会では、各受賞学生の応募論文についてのプレゼンテーションと質疑応答のほか、「2024年に向けた未来会議」と題し、2024~2050年の社会を見据えて策定した住友理工が実現したい未来像を説明した後、2050年はどのような世界になっているか、その中で自分はどうなっていたいか、住友理工の未来像に共感できるかなどの意見交換を実施しました。
今回で記念すべき10回目となる本アワードですが、1回目からの応募総数は768本、そして合計76本の論文を表彰してきました。
その受賞者の中には、本アワードで論じたこと、探求したことをきっかけに、日本だけではなく、海外や様々な最先端の業界で活躍をされている方が何人もいます。そんな皆さまからは、「このアワードで受賞したことが今のキャリアに繋がっている」などの嬉しい声もお寄せいただいています。
また、当社も受賞学生との懇談会を通して、今の若者の文化や発想に触れることにより気づかされることも多く、学生という次世代を担うステークホルダーとの対話を通じて、企業が目指すべき姿や、学生たちが関心を持っている社会課題などを知る大変貴重な機会となりました。





